神田駅近くの名店「味坊」へ
下町で飲むから来いとtwitter界隈のお友だちに誘われたので行った。
向かったのはJR東京駅のお隣・神田駅近くで名店と名高い中華料理店「味坊」。ご一緒したのは安ワイン道場師範、mashi-comさん、そして幹事のゆうこりンファンデルさんの3名だ。

mashi-comさんとは初対面、あとのお二方とはすっかりお馴染みというメンバーで、好きなのはワインである以前にまず酒、みたいなオーラをまとったみなさまだ(私もだ)。
集合時間は外がまだしっかり明るい5月の午後4時半。漂う「今日は飲むぞ」という空気感。剣豪が鍔迫り合いをする間合いでもってビール、レモンサワー、ハイボールといった得物を掲げて乾杯である。この飲み会、いい(悪い)予感しかしない……! あとレモンサワー超うめえ…!
【味坊自然派ワイン1】リヴァトン「パノラミック」
さて、味坊は普通のというかむしろ普通以上に気取ってない感じの街の中華料理屋さんなのだが、自然派ワインに力を入れている。中華料理店によくあるタイプの横開きの中身の見える冷蔵庫あるじゃないすか。ビールとかサイダーとか、オレンジジュースとかが入ってるASAHIとか書いてありがちなやつ(味坊のビールはサントリーでしたが)。あんな感じの業務用冷蔵庫にどれくらいかな。30本くらいかな。それくらいの数のワインがミチミチに詰められている。

リストはなく、ボトルネックに巻かれた産地や品種、生産者などの情報が書かれた紙と、ボトルにマジックで直接書かれた金額、あとはもちろんラベルの情報を頼りに選ぶスタイル。
これだ! というのが決まったら、冷蔵庫から勝手に引っ張り出して申告すると店員さんが抜栓してくれる。価格帯は4000円弱から、高いので6600円っていうのがあった。
乾杯の飲み物を飲み干すタイミングで「せっかくだしひとり1本ずつ選びましょうか」ということになり、まずは安ワイン道場師範が先頭バッターとして選んでくれたのが南仏・ルーションの造り手、リヴァトンの「パノラミック」というワイン。シラーを使ったロゼペティアン(微発泡ワイン)というちょっと珍しいシロモノだ。

ワイングラスはなく、注ぐのはビール用のコップ。飲み口は厚く、香りが滞留するふくらみもない。ワインを飲む器としてはベストではないだろう。でもこの雰囲気だとなんかいんですよこれが。こないだ観たジョージアの古い映画では牛かなんかのツノで飲んでたし。ワインには時と場所にふさわしい器があるのだ多分。

さて、このワインはぷちぷちした細かい泡が楽しい明るいワインで、わりと全会一致で「梅酢!」という印象。なんならちょっとシソ入れた? くらいの感じのロゼだ。ロゼにするとシラーのスパイシーさがなくなって甘酸っぱい感じに仕上がるんですかね。おいしい。

酸っぱいだけでなく果実味もちゃんとあるので中華にピッタリ。スペシャリテのラム串と合わせると飲む調味液化しておいしさをさらに高めてくれた。炒めた海老ともピンクつながりでよく合った。海老とロゼ、いいよなぁ。
【味坊自然派ワイン2】シャトー・レスティニャック「ヴァ・トゥ・フェール・ボワール 」
続いてじゃあ次は私が……と冷蔵庫へと向かってくれたのはmashi-comさん。なんですかねこれ。この一人ずつ席を立ち、ワインを連れて帰ってくる感じが大変楽しい。毎回「そうきましたか〜」みたいになるのが良い。なぜかみんなちょっとニヤニヤしてるし。

そんなこんなでmashi-comさんに連れられてテーブルにやってきた2本目はボルドーの東・ベルジュラックの生産者、シャトー・レスティニャックがつくる「ヴァ・トゥ・フェール・ボワール 」というワイン。無清澄、ノンフィルターで亜硫酸の添加もごくわずかという造りでこれがとってもおいしかった。
メルローってこんなにかわいらしい味だったっけ? というくらい渋みおだやか、酸味そこそこ、果実味たっぷり。ボルドーから夏の休暇でやってきたリラックスモードのメルローといった印象だ。
「ヴァ・トゥ・フェール・ボワール」ってどういう意味ですかねと携帯で調べると、出てきた答えは「酔っ払う」だそうで、今の我々にこんなにふさわしいワインはありませんなダハハと爆笑しながらコップで飲むワインがうーん、うまい。
これは推せる↓
【味坊自然派ワイン3】ヴァイングート・スルーナー「トーニ」
さて、3本目は私チョイス。ロゼ泡、赤ときて、4本目は赤になる可能性が高いことから、白を頼むチャンスはここしかない! と、オーストリアのグリューナー・フェルトリーナーを選んでみた。

造り手はヴァイングート・スルーナー。キュヴェ名のトーニ(TONI)は当主のファーストネームだそうで、Tasty、Original、Natural、Indivisualの頭文字でもあるみたいなことなんだって。あいうえお作文かよ。
Masi-comさんの「グリューナーって当たらないし外れないですよね」という言葉が至言で、このワイン自体にガツンとしたインパクトはないものの、さりとておいしくないこともまったくなく、なんかこう、ワインだっつーのにチェイサー感まであるというワインだった。師範は「甲州みたいだよね」と評していたが、それも納得。ただ、それだけにとうべきかこれも中華とは好相性で、その点はとても良かった。
【味坊自然派ワイン4】デスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス「パタロス」
最後にゆうこりンファンデルさんが選んだのはスペインのメンシア。ファンデルどこいった。造り手はデスセンディエンテス・デ・ホセ・パラシオス。有名なアルバロ・パラシオスと、その甥のリカルドが立ち上げたワイナリーだそうで、キュヴェ名「パタロス」は花びら的な意味だそうだ。

メンシア95%、バレンシアナ/パロミノ計3%、アリカンテ・ブーシェ/他 計2%というセパージュで、渋みと酸味が主体の構成。間違いなく温度が上がって果実味が出てきてからが本番みたいなワインだと思われるが果実味選手がブルペンで肩を温めている間に(一瞬でぜんぶ飲んじゃって)試合終了となってしまった。これだから酒飲みはさあ……。

「安ワイン道場」の稽古日誌でも言及されていたが、この日飲んだ4本の自然派ワインはどれも「キレイな造り」とか「(素人に検知できる範囲で)ネガティブ要素がない」みたいに言われるであろうタイプのワインたちで、おしなべて料理との相性が良かった。その料理のクオリティも価格に対して評判通りに高く、味坊が名店と呼ばれるのにも納得。また必ず来たいお店となったのだった。
【延長戦】亀戸の名店・デゴルジュマンへ
さて、この時点で一人ワイン1本+レモンサワー等を消費しているので、他の方はともかく私は完全にできあがっている(私の普段の晩酌はボトル1/3程度)。しかし空にはまだ沈んだばかりの太陽の余韻が残り、夜はこれから。二軒目として亀戸のシャンパンバー・デゴルジュマンへと向かった。
神田から秋葉原までを夜風に吹かれつつ歩き、秋葉原から総武線に乗れば亀戸まではあっという間。北口を降りてすぐの亀戸横丁の喧騒を抜ければそこには泡パラダイスが待っている。店主・泡大将と助手・ソムたまさんに笑顔で迎えられ、まずオーダーしたのはシャンパーニュ3杯セット1800円。

3杯かける4人で12個のグラスがカウンターに並び、そこに定規で引かれた線のようにシャンパーニュが注がれていく様子が美しいんだよなぁ。「ワインをグラスに注ぐ」ただそれだけのことでもプロの仕事はレベルが違う。お外で飲む楽しみのひとつですね。
さて、泡大将いわくこの日の3杯はすべて醸造家、エルヴェ・ジェスタンが醸造コンサルタントを担当したものなんだそうだ。エルヴェ・ジェスタンは「ビオディナミを現代的に解釈」した醸造家とのことで、この日飲んだキュヴェは以下の通りだ。
べナール・ピトワ カルト・ブランシュ ブリュット
べナール・ピトワ ロゼ ブリュット
ルクレール・ブリアン ブリュット レゼルヴ

べナール・ピトワは10ヘクタールの畑を所有する小規模生産者で、自分たちでシャンパーニュを造りつつ、果汁をボランジェ、ポール・ロジェ、デュバル・ルロワなどのメゾンに販売もしているそう。エルヴェ・ジェスタンはデュバル・ルロワで20年にわたり醸造長を務めた人物とのことなので、コンサルしてるのはそのつながりだったりするんですかね。
ルクレール・ブリアンはもともと自然派シャンパーニュの元祖といわれる造り手だったのが後継者不足から大手グループの傘下に入る寸前、エルヴェ・ジェスタンらのグループが買い戻したんだそうで、それ以降畑をビオディナミ化して品質がさらに上がったみたいなことがネットを見ると書いてある。
と、駆け足で調べたことをまとめてみたが、こんな興味深い3杯を1800円で飲み比べられるのがうれしい。

べナール・ピトワのカルト・ブランシュはシャンパーニュのお手本のような繊細な香りと厚みのある味わい。ロゼはそこに酸味と果実味が加わってどちらもすごくおいしい。
ルクレール・ブリアンのほうは、まさに「ワインとしておいしい」という感じのシャンパーニュ。味わいの密度が高くて、乾杯用というより食事と合わせてじっくり楽しみたい、風格のある一杯だった。

このセット、いつも満足だがこの日のはとりわけ満足度が高かった。エルヴェ・ジェスタン、覚えておきたい名前がまたひとつ増えたのだった。
バタフィー、ブシャール、パルム・ドール……
さて、すでにほぼ完璧に酔っ払っているところにそれぞれはハーフサイズとはいえシャンパーニュを3杯入れてしまったのでここからは記憶があいまいだが、次に飲んだバターフィールドのボーヌ プルミエ・クリュ ル・ブレッサンド2019がおいしかったのは間違いなく脳裏に刻まれている。

いるのだが、私のメモに残っているのは「バラ」「完全にバラ」「本当にバラ」というまさかのバラ3連発。貴様にバラ以外の語彙はないのか。酔っ払った私が感知できるのは「バラか否か」の一点のみでありこのワインはバラだ。
カメラロールを見返してなんでこの状態からさらにオーダーしたんだと己に問いたいのだがその次にはブシャール・ペール・エ・フィスのブルゴーニュ ピノ・ノワール コトー・ド・モワンヌ2019をオーダーしたようだ。

このあたりはメモが錯綜しており、どのコメントがどのワインについて語っているのかがもうわからない。「2019は2017に次いで最近のブルゴーニュではいい年」とのことでこのワインも端正でおいしいピノ・ノワールだった記憶がうっすらある。すみませんまた改めて飲みます……。
そして16時半からはじまった会も気がつけばこの時点で何時だったんだろう。21時を回っていたのだろうか。時間という概念がアルコールの浸透圧で溶解したダリ的世界観のなかで最後にいただいたのはここにきてまさかのプレステージシャンパーニュ、ニコラ・フィアットのパルムドール・ロゼ2006! 安ワイン道場師範のおごりだ。こういうのがサクッとできるのカッコいいよなー。ごちそうさまです。

色は赤に近いピンク色で、甘酸っぱさのなかに熟成したシャンパーニュの香りがしっかりとあったことだけ鮮烈に覚えている。手元には「ものすごく品の良いランブルスコ」というメモが残っているがシャンパーニュにもランブルスコにも失礼な感じがするなこの感想。いずれにせよ、これだけ酔っ払っていてもなお脳裏に焼き付く素晴らしいシャンパーニュだった。

というわけで開始からは5、6時間くらいだろうか。ひたすら飲み続け、笑い続けた宴は終わった。宴というか、手触りとしては「祭」という言葉がふさわしいような夜だった。祭りとはなにかを祝福するためのものだ。ワインよ、地球に存在してくれてありがとう。
そしてなにしろお誘いいただいてありがたい。大人数で飲むのはもちろん楽しいけど、少人数で飲むのもやっぱり最高。みなさん、また飲みましょう!
![ヴァ・トゥ・フェール・ボワール [2020] シャトー・レスティニャックChateau Lestignac Va te Faire Boire ヴァ・トゥ・フェール・ボワール [2020] シャトー・レスティニャックChateau Lestignac Va te Faire Boire](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/maruyamaya/cabinet/image/france/bordeaux/_mg_8106_1.jpg?_ex=128x128)
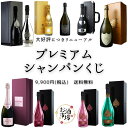
![【母の日 ノーベル賞晩餐会提供シャンパンブランド】テタンジェ ノクターンスリーヴァーグラスセット [ スパークリングワイン フランス 750ml ] [ギフトBox入り] 【母の日 ノーベル賞晩餐会提供シャンパンブランド】テタンジェ ノクターンスリーヴァーグラスセット [ スパークリングワイン フランス 750ml ] [ギフトBox入り]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Na9e6+QwL._SL500_.jpg)